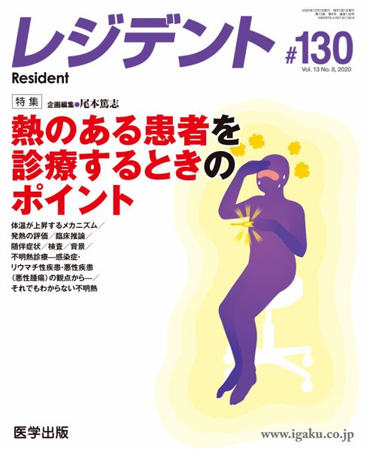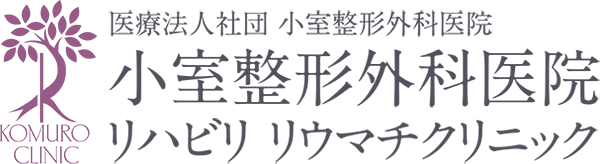リウマチ膠原病外来について

関節リウマチと膠原病
体をウイルスや細菌から守るために働く免疫細胞が、間違って自分自身を攻撃してしまう病気は「自己免疫疾患」と総称されますが、その中で全身の臓器や関節などに病変をきたすものを「膠原病」に分類します。頭の先から足の先まで、体のあちこちに炎症や障害が起こる可能性があります。症状は、関節や筋肉の痛み、発疹、発熱、咳、腹痛、目のかすみなど、人それぞれです。
ところで、「関節リウマチ」は膠原病の一種です。関節の炎症が持続的に続き、軟骨や骨が破壊されていく病気です。ほうっておくと、関節が変形してしまいますが、しっかりと診断・治療を行うことで、現在は「進行の予防が期待できる病気」となりました。
当院の治療方針
薬物療法・手術・理学療法(リハビリテーション)・環境調整・合併症治療の5つの治療を組み合わせたトータル治療を方針にしています。
当院では、整形外科と内科、両方の日本リウマチ学会専門医(指導医)が治療にあたります。整形外科医の院長は、主に関節リウマチによる関節炎の痛みに対する治療や、破壊された関節の手術、リハビリテーションを担当。内科医の尾本が投薬治療を担当し、生物学的製剤やJAK阻害剤を用いた先端治療も取り入れています。整形外科医と内科医が、それぞれを補完し合いながら治療を行うことで、最大限の効果やリスクの最小化を図っています。合併症治療は必要に応じて、専門医を紹介します。
また、リウマチケアナースが所属し、患者様の治療計画のサポートや生活状況の把握、患者様の相談相手になれるように努めています。理学療法士は関節リウマチのリハビリテーションも専門とし、管理栄養士は骨粗鬆症に対する栄養指導を行います。地域連携室は他施設や介護サービスとの連携をサポートしています。
病気に対する治療だけでなく、その方が求める日常生活の支援も含めた治療を行いたいと考えています。
膠原病の代表例
- 関節リウマチ
- 全身性エリテマトーデス
- シェーグレン症候群
- 強皮症
- 多発性筋炎
- 皮膚筋炎
- 混合性結合組織病
- 抗リン脂質抗体症候群
- 血管炎症候群
- 成人スティル病
- ベーチェット病
- サルコイドーシス
- 乾癬性関節炎
- 手や体の関節にこわばりがある。
特に、朝起きてすぐに手や体を動かしにくい。 - 関節に痛みや腫れ、熱感がある。
(左右対称に関節に炎症が生じたり、炎症部位が移動したりすることもある。) - 倦怠感がある。
- 37℃以上の発熱が続く。
- 食欲がなく、体重減少が続いている。
- 皮膚に発疹や赤い膨らみができる。
- 指先が白くなる。
- 手足のしびれがある。
- 眼や口が渇く。
- 咳や息切れがある。
当院のリウマチ科(膠原病外来)の治療の特徴
- 整形外科と内科、両方の日本リウマチ学会リウマチ専門医(指導医)による治療
- 生物学的製剤やJAK製剤といった先端治療も可能
- その方の生活状況に応じた治療の組み合わせ(投薬・リハビリ・手術・環境調整)
- メリット・デメリットを情報共有し、治療計画について患者様と共同で意思決定
- 合併症や併存症(かかっている他の病気)に対する同時治療および専門医紹介
当院の関節リウマチの専門治療
【院長コラム】最初の主治医、関節リウマチ患者
平成5年5月に医師国家試験の合格通知があり、研修医として母校の大学附属病院の整形外科として働きはじめた。
点滴や採血係からはじめて、最初に病棟医長の先輩医から主治医として受け持ちを申し渡されたのは、33歳の関節リウマチに罹患した患者だった。今でこそ関節リウマチという病気は「寛解」という症状が消失する状態に治療できる疾患であるが、当時は痛み止めとストロイド、関節が崩れてくれば手術する、それでも進行はとまらず、身体障害がすすんでいく不治の病であった。
受け持ちになった方は16歳で発症し、体中の関節がぐらぐらになっている状態であった。ずっと大学病院で治療を継続されていたのだが、最後の入院は自宅でトイレに入って前かがみになった時に骨破壊が進行していた頸椎がずれて、延髄を圧迫し呼吸が一気にとまった状態で発見され、救急搬送されたが、もちろん意識が回復するはずもなく、最後の看取りをする医師として新米研修医が選ばれたのであった。
入院して3日、私の仕事はただ点滴を交換し、人工呼吸器を観察し、モニターをみて記録をつけるだけの仕事であった。最後の日は深夜に心電図モニターのレートが徐々に伸び、心停止にいたり、当直の先輩ドクターを呼び、一緒に型どおりの心臓マッサージを施行した。関節リウマチでぼろぼろになった体は、胸郭を圧迫するたびに肋骨がパキパキと折れ、口からは血液がまじった泡がとびだしていた。二人暮らしをしていたお姉さんが到着した時には完全に心臓も停止し死亡確認したあとだった。最後の体重は30kgを切っていたと記憶している。最後の心臓マッサージで肋骨が折れる感覚は今も感触は覚えている。
それから2年後、愛媛県の松山赤十字病院のリウマチセンターで関節リウマチを診る修練をはじめて、今に至っている。
現在は関節リウマチは「なおる」病になった。リウマチの方を治療しなければいけないという、私がリウマチ治療を一生やっていく原点になっている。
【尾本Drコラム】関節リウマチ・膠原病と向き合っていく
リウマチ専門医を選んだ理由

私は1996年に京都府立医科大学を卒業しました。学生時代は決して真面目なほうではなく、読書と麻雀と音楽鑑賞で大半の時間を費やす生活でしたが、学生時代は「病気を診る」ことよりも、「患者を診る」ことに大変興味を持ち、卒業後は、当時その考えを実践されていた京都府立医科大学第一内科に入局いたしました。
内科全体を網羅する形で、初期研修の2年間を過ごし、その後の4年間を社会保険神戸中央病院内科医院として、引き続き内科全般の診療に携わりました。その中で僕がリウマチ膠原病医を選んだ二つのきっかけがありました。
一つ目は、研修医になって、初めて担当になった患者さんが、当時高校三年生の膠原病(全身性エリテマトーデス)患者でした。1か月間の入院でしたが、退院翌日から中間テストがあるとのことで、数学や英語を教えたりしながら、診療を行っていたのを覚えています。その時に、「この患者さんは、この先長い人生を、この病気とともに歩んでいくのだな」と思うと、リウマチ、膠原病のような、当時原因不明で、完治できる治療法がない、比較的若い方が罹患する病気に、向かい合っていきたいと漠然と考えておりました。
二つ目は、医師6年目の時です。当時神戸にいた僕に、イギリスに留学していた妹から電話で連絡があり、「関節リウマチにかかったみたい。治療するなら帰国したほうがいいといわれた。」とのことでした。結局妹は留学を断念し、帰国しました。症状が落ち着くまで、しばらく僕の自宅で居候することになりました。2001年当時の関節リウマチの治療は、まだ日本では発展途上でしたが、すでに欧米では、現在は当たり前になった、生物学的製剤が使用可能となっており、驚異的な効果を報告されていました。そこで、なんとか痛みに苦しむ妹を治してあげたい気持ちと、これから新規の治療薬が出てくるリウマチ膠原病性の疾患を一生の生業にしたいという思いが強くなりました。
以上、二つのきっかけがあり、医師7年目からリウマチ膠原病を専門にすることになりました。
リウマチ内科医になって
医師7年目に、京都府立医科大学膠原病アレルギーリウマチ内科に所属し、そこで通常診療と、大学院での研究を開始しました。大学在学中に生物学的製剤(レミケード® )が日本でも使えるようになり、まさに衝撃的な効果を実感しました。それまでは本当に苦労していたリウマチ治療が、幾分かやりやすくなりました。それでも、副作用の懸念、すでに完成してしまった関節変形を治すすべは内科的にはなく、やはり限界も感じておりました。できるだけ早期からのしっかりとした治療の必要性を実感する毎日でした。
大学院の研究では、血清の銅をキレートする薬剤が、関節炎モデルラットで非常に効果があることを示し、ヨーロッパのリウマチ専門の医学誌に掲載されました。
京都第一赤十字病院での診療
大学院を終了後、2006年から京都第一赤十字病院糖尿病内分泌リウマチ内科の医長として勤務することになりました。当時はリウマチ膠原病を診る医師が京都府全体で非常に少なく、毎日のように紹介患者さんが舞い込んできました。当時は関節リウマチと膠原病の患者さんあわせて500名程度でしたが、毎年どんどん増えてきて、2014年には京都府で初めてリウマチ膠原病センターが開設され、現在は2000名を超える数になっています。そのセンター員として、私自身800名前後の患者さんを担当しています。
幸い、この十数年間の間に、関節リウマチの治療薬は非常に選択肢が増えてまいりました。いわゆる後発品のバイオシミラーを除いても、生物学的製剤は8種類になり、また、新しい機序のJAK阻害剤も5種類が使用可能となっております。また、それ以外にも安価で比較的安全に効果が望める抗リウマチ薬や、関節リウマチの関節破壊を抑制する効果のある、骨粗鬆症のお薬なども使用可能となっており、我々内科系のリウマチ専門医にとってみると、大変ありがたい状況です、関節リウマチを患う患者さんにとっても、大きな福音をもたらすことになりました。
また、関節リウマチと比べると、新規薬剤の開発が遅れていた膠原病疾患に対する治療薬も、ここ数年で飛躍的に選択肢が増えました。新しい機序の免疫抑制薬や、生物学的製剤が使用可能となり、膠原病患者さんにとっても、疾患がコントロールしやすい時代になってまいりました。
これで、すべてのリウマチ膠原病患者さんが毎日笑顔で、普通の方と全く同じ人生を歩んでいけるようになったかというと、そうでない部分もあることも事実です。また、リウマチ専門医の診療も非常に簡単になったかというと、そうではありません。
いつの時代になっても、リウマチ膠原病診療で、もっとも大事になってくるのは診断になります。医療の進歩により、以前に比べると関節リウマチ、膠原病の診断は比較的容易になってきていますが、それでも非常に悩む症例は存在します。そういった場合に、リウマチ専門医は、他の疾患の知識も必要になります。原因不明の痛みや、発熱の患者さんが「リウマチ、膠原病疾患でしょうか?」と紹介される機会があります。その際に、「リウマチ、膠原病ではなさそうです」という返事はできても、それでは、紹介してくださった医師、また、患者さん自身にとってみると、それは何の解決にも至っていません。リウマチ膠原病疾患をしっかり診断することはもちろん非常に大事になりますし、僕らの使命でもありますが、それと同時に、「リウマチ膠原病ではないですが、~だと思います」と、しっかり道筋を立ててあげることも大事になると思っています。それには、いわゆる総合診療的な知識が必要となります。
また、多数の薬剤が使えるようになっても、問題となるのは安全性です。新規の薬剤については、常に副作用の懸念がありますし、様々な背景をもつ患者さんに対して、一人一人、より適切な対応を必要とされます。それには、やはり他の疾患の知識や、各臓器の知識、整形外科的な知識も要求されます。
そして、いまだ完治にいたる特効薬は見つかっていないため、関節リウマチ、膠原病、ともにほぼ一生お付き合いしなければならない疾患のままです。そうなれば、そういった疾患を持ち続ける患者さんの心理的な側面や、慢性の痛みや、倦怠感など、そういった残存する症状に対するアプローチも重要になってきます。
そういった様々な知識と経験、アプローチが要求されるリウマチ膠原病疾患でありますので、私は、リウマチ膠原病の専門ではありますが、2014年に京都第一赤十字病院で総合内科を立ち上げることにしました。現在はそこの責任者として、リウマチ膠原病患者、その他、慢性疼痛、原因不明の症状を持つ患者さんなどの診療を行っています。
当クリニックでの診療体制
このたびご縁があり、2020年1月から当クリニックで、毎週水曜日の夜診で、リウマチ膠原病外来を担当させていただいております。
主に、関節リウマチ、膠原病の患者さんを診察いたしますが、生活習慣病なども含め、内科全般の診療もさせていただいております。また、原因不明の痛みや関節痛などの患者さんの診療も行っております。
僕が考える診療スタイルは、小室院長と同様に、トータルマネジメントが信条です。病気を診るのでなく、人を診るという気持ちを強く持って、診療にあたっています。できるだけ患者さんの症状を軽減するために関節の症状が強い方については、同じくリウマチ専門医であります院長のサポートも得ながら行っています。
幸い、当クリニックは、関節リウマチ、膠原病に対して本邦で使用可能な薬剤のほとんどを投与することができます。このような環境に恵まれたクリニックは京都でもほとんどないと思います。
もし万が一、入院が必要となるような病状の際にも、普段勤務している京都第一赤十字病院や、これまで培ってきた人脈を生かして、他の総合病院に勤務するリウマチ専門医への依頼なども可能な体制になっております。
当クリニックで、地域住民の方々に少しでもお役に立てるよう、微力ながら頑張っていきたいと思っております。
著書
レジデント(Resident) 第130号
特集●熱のある患者を診療するときのポイント
企画編集/尾本篤志